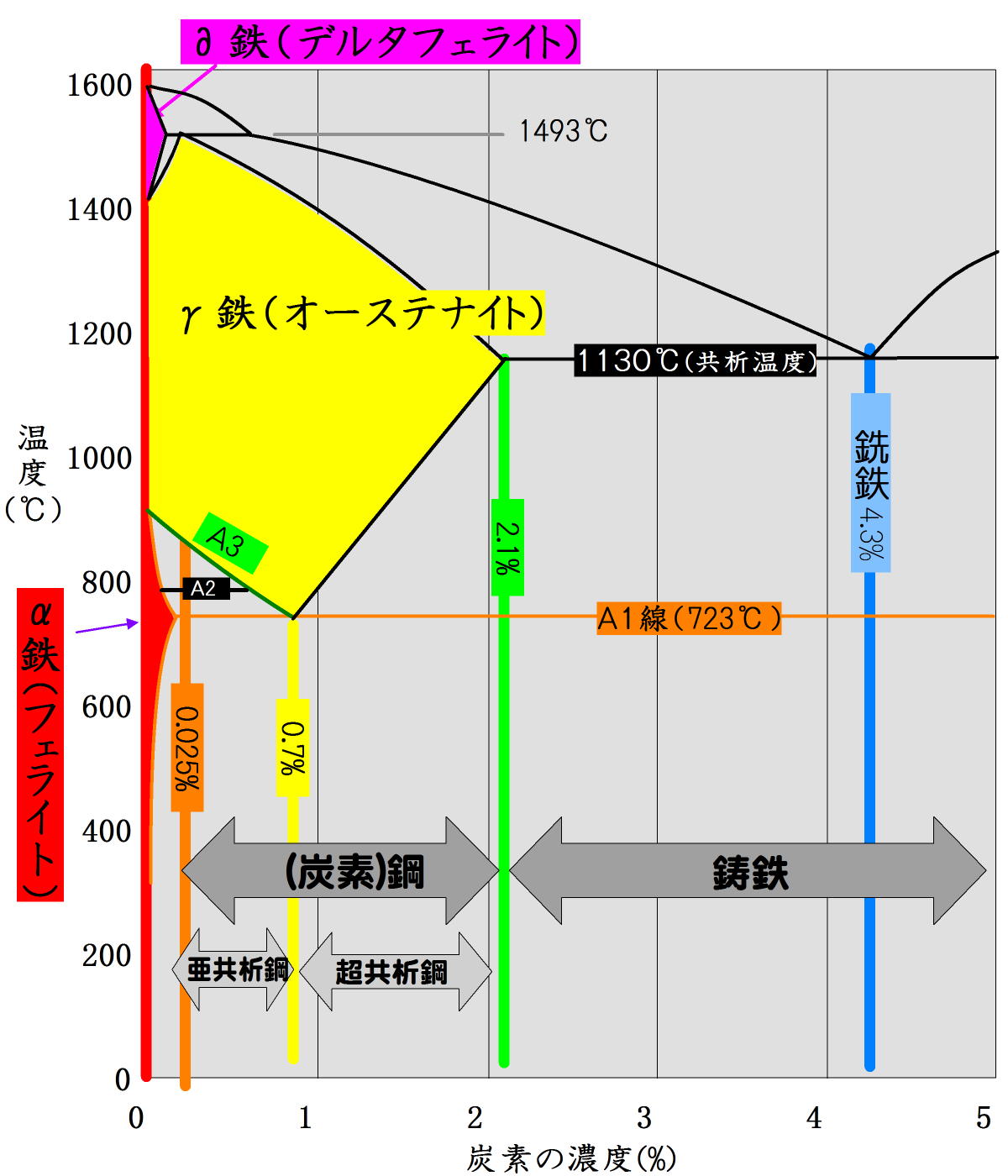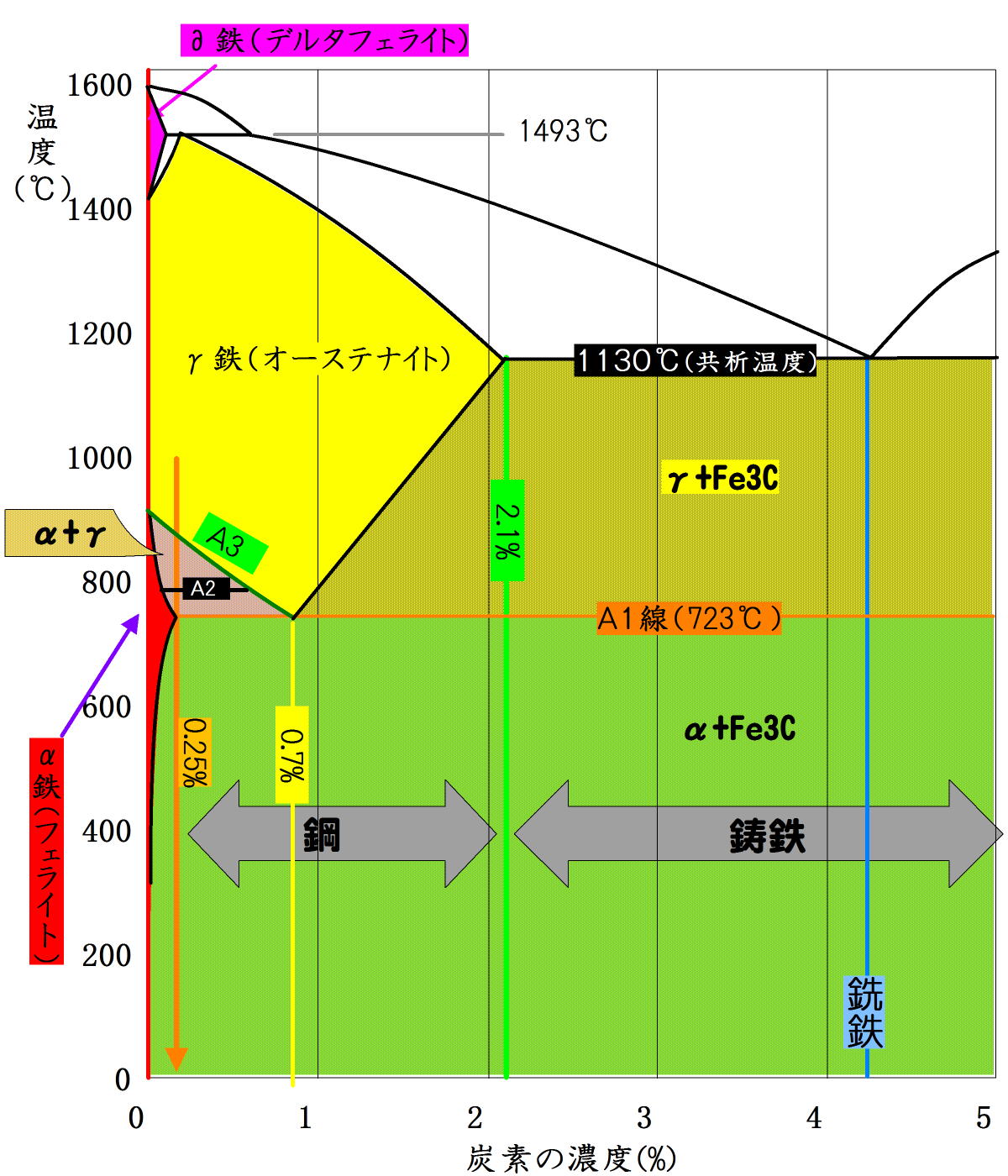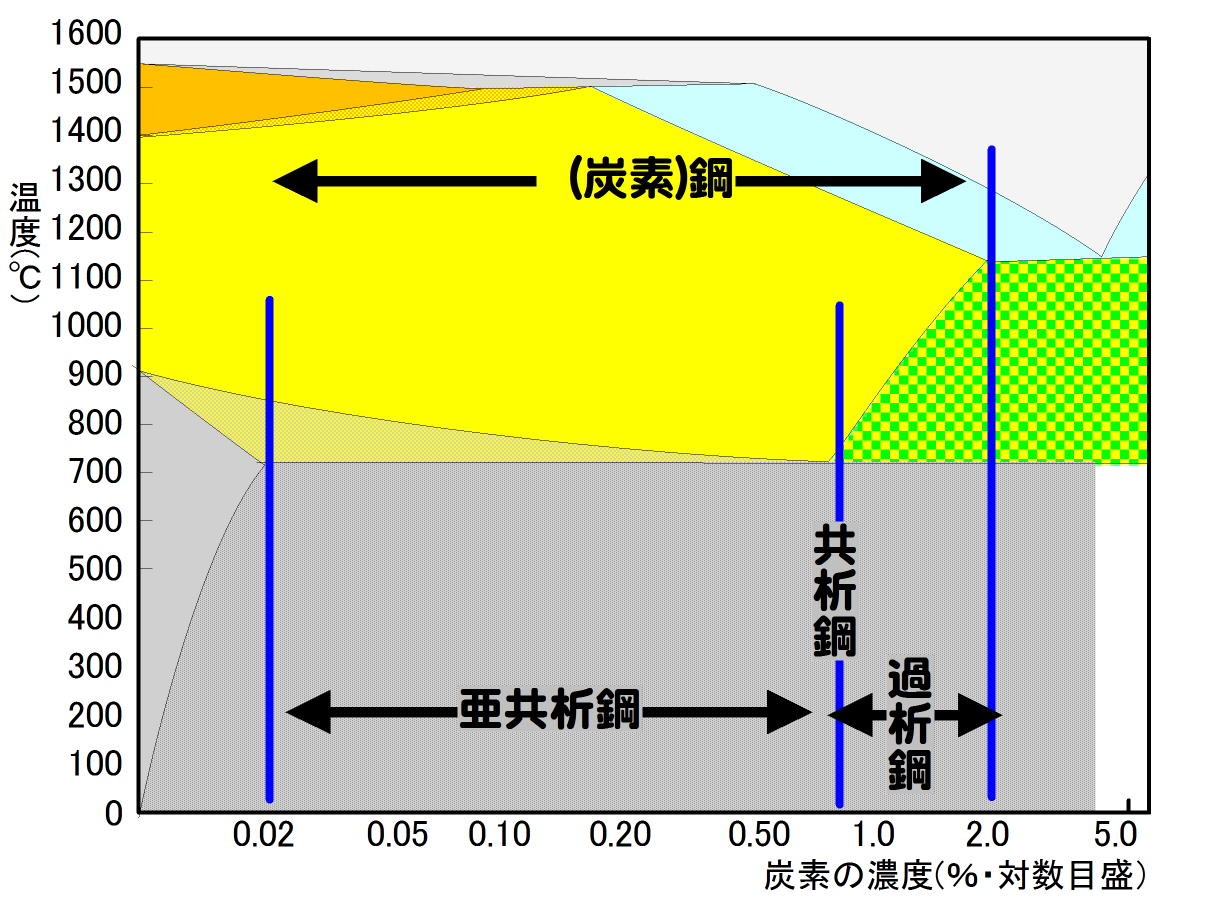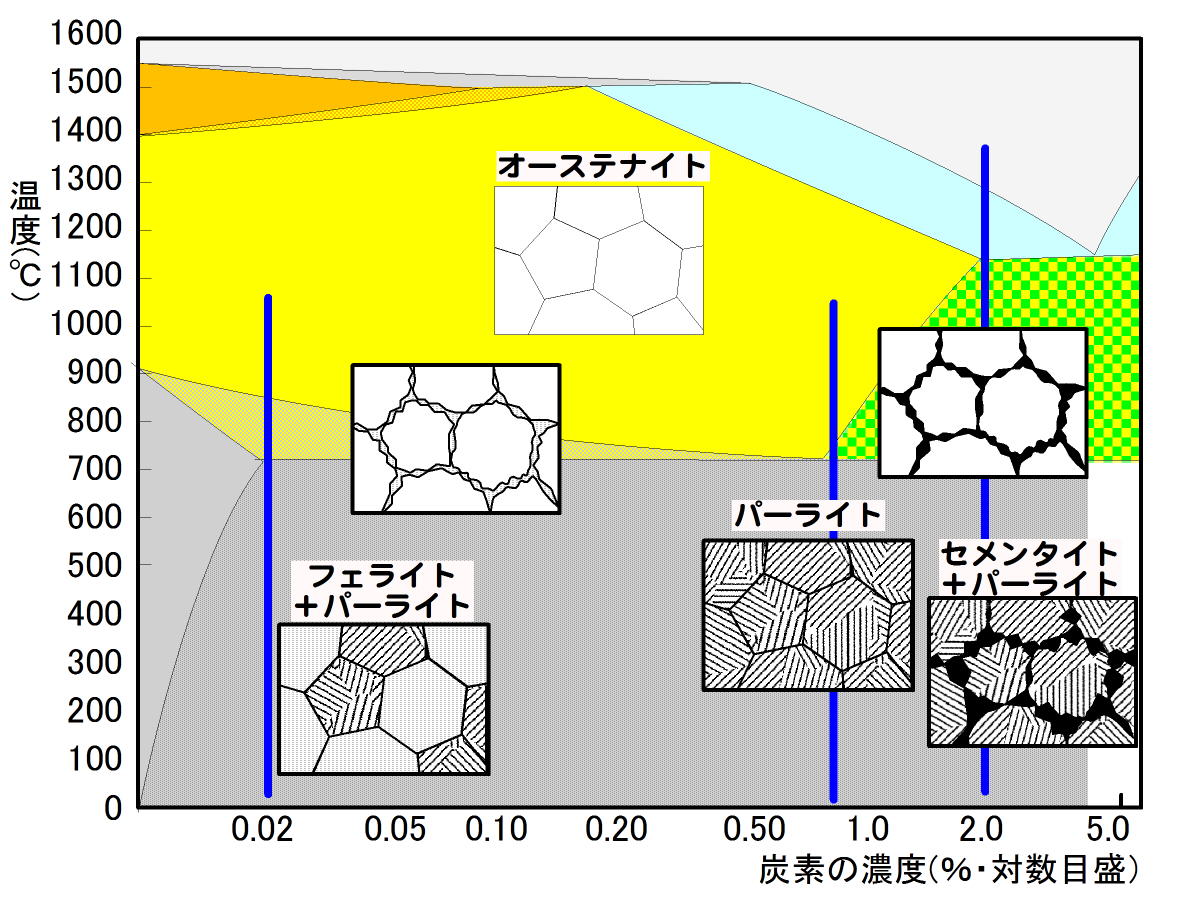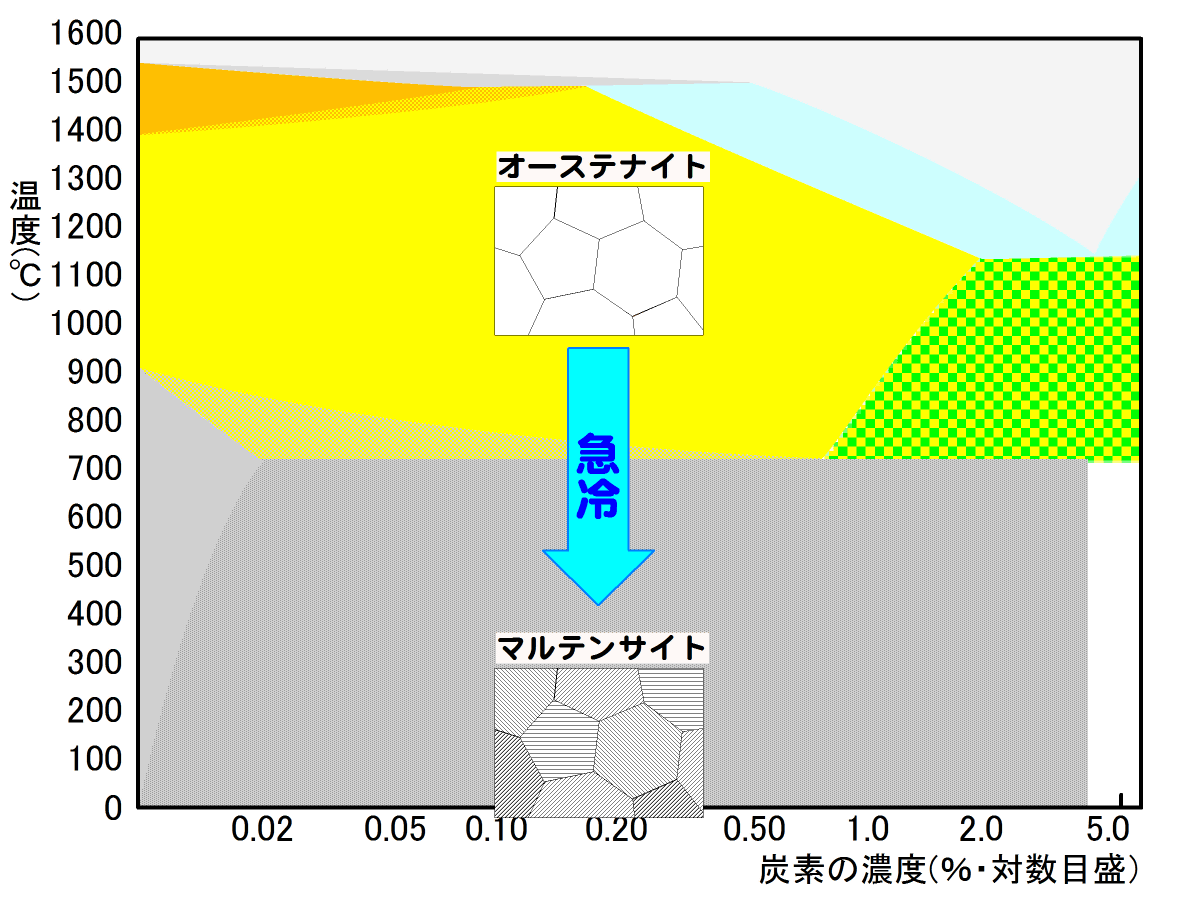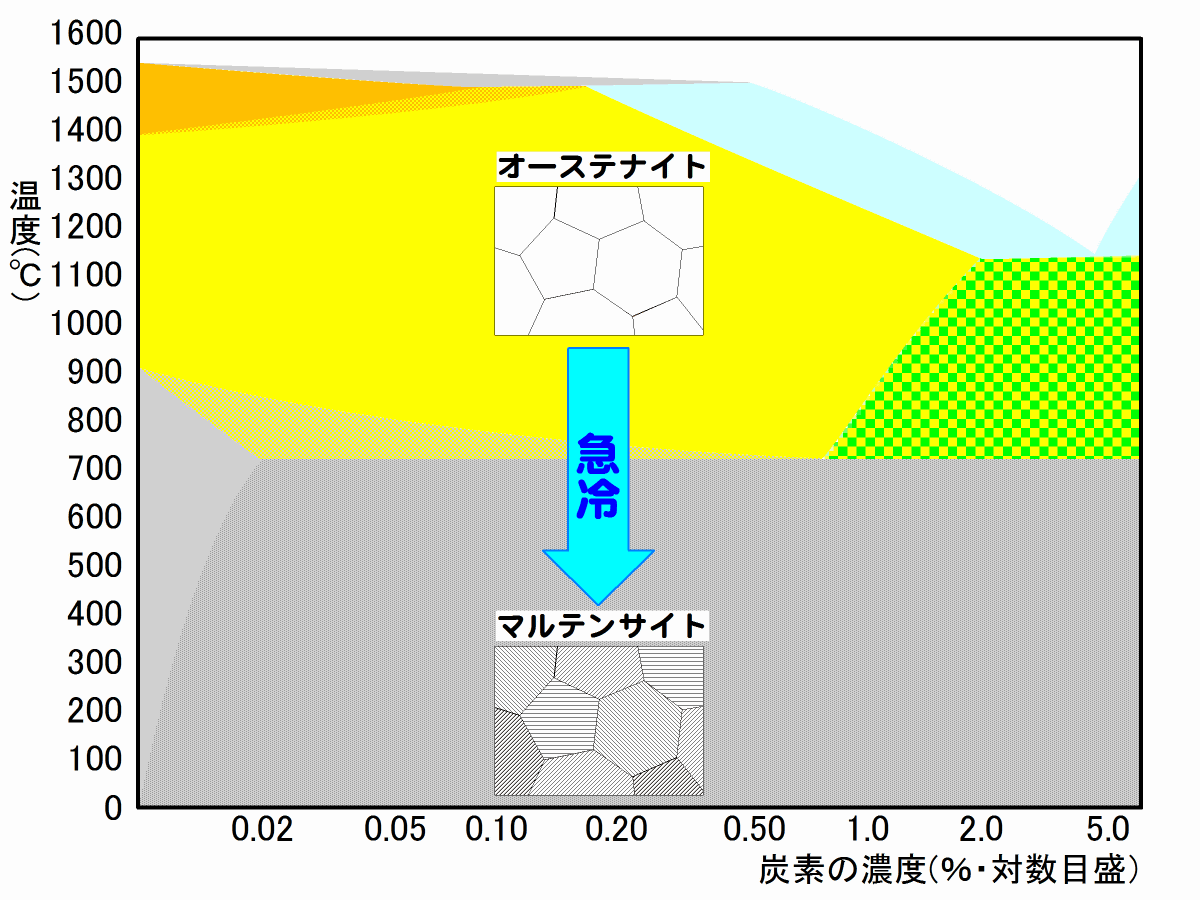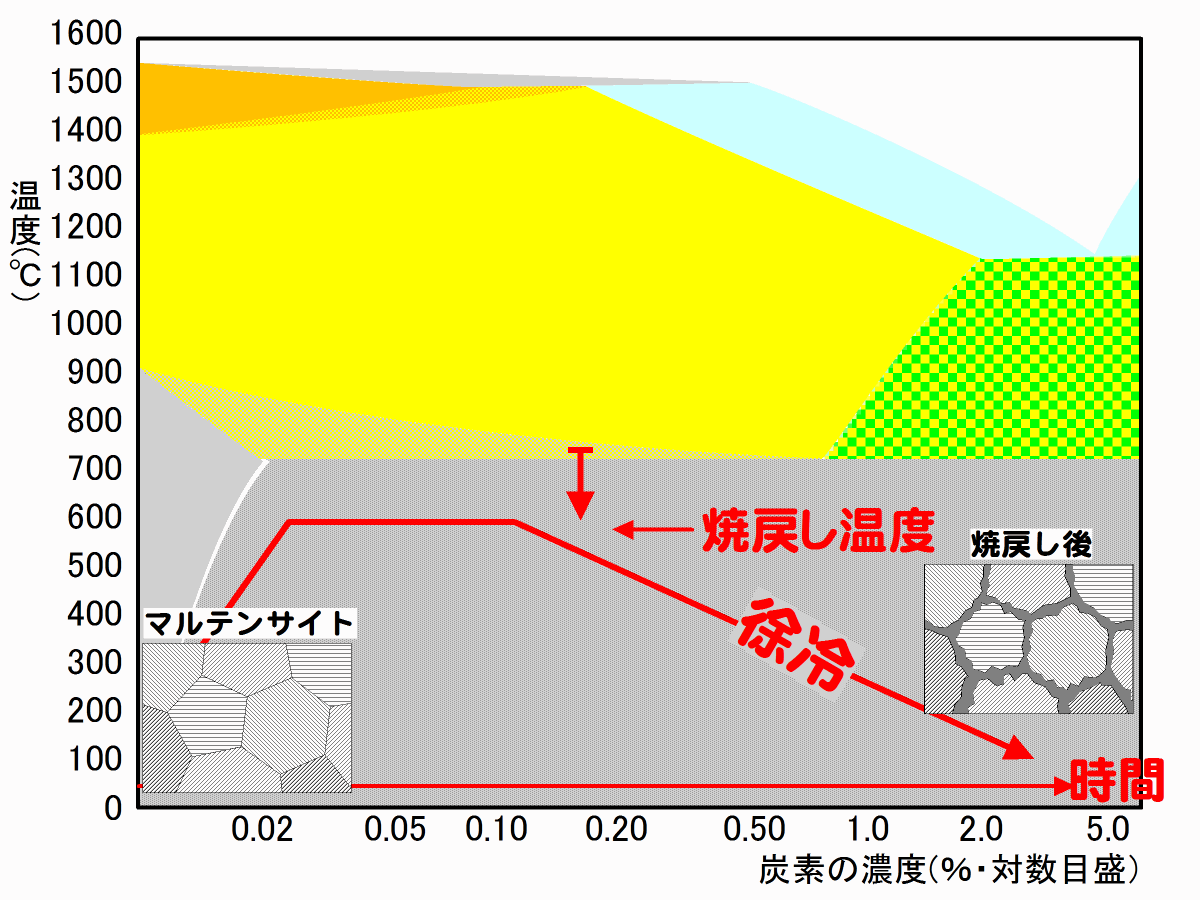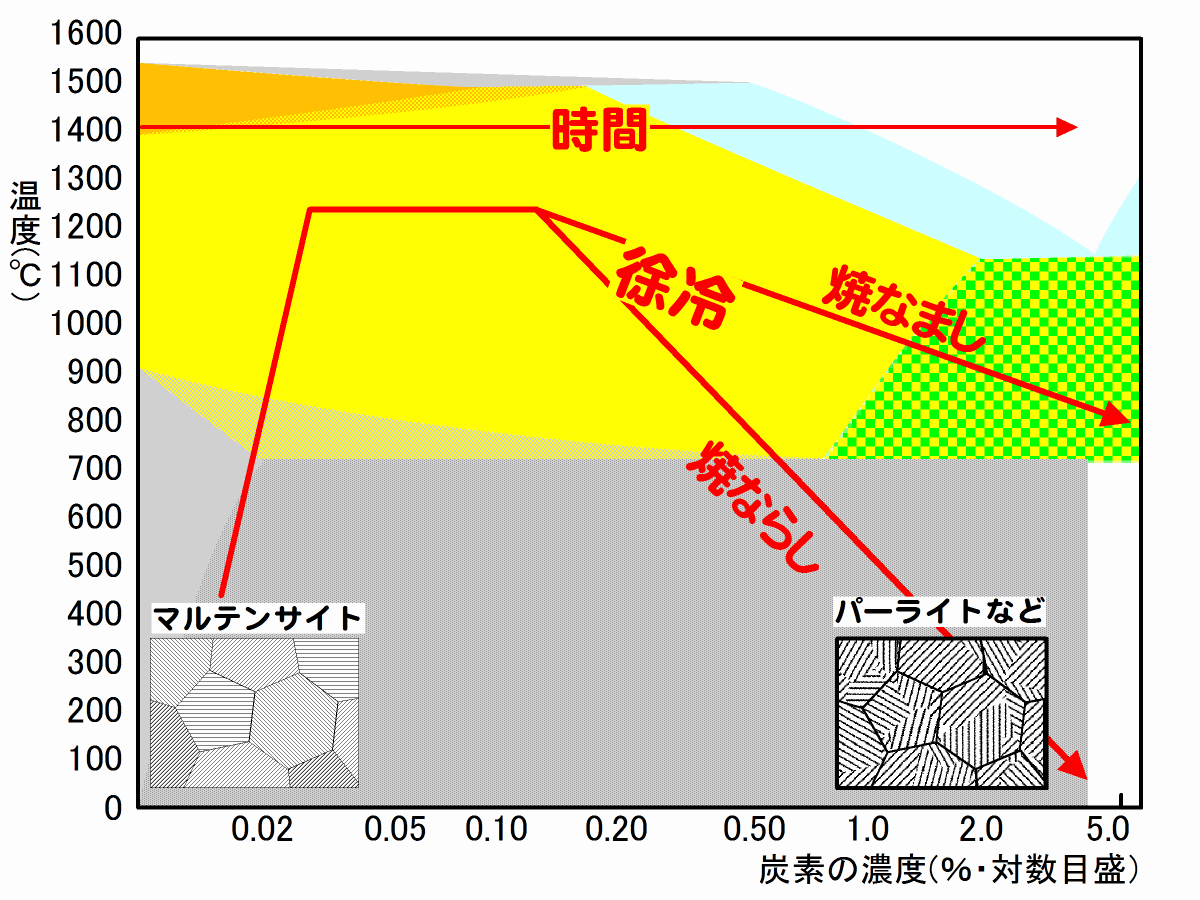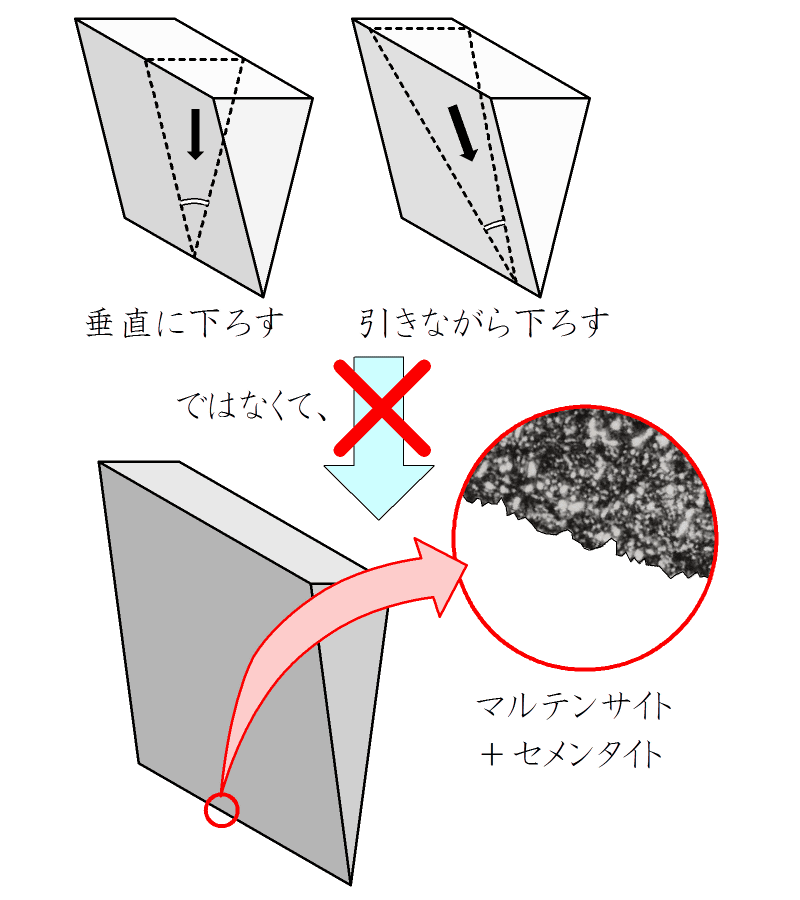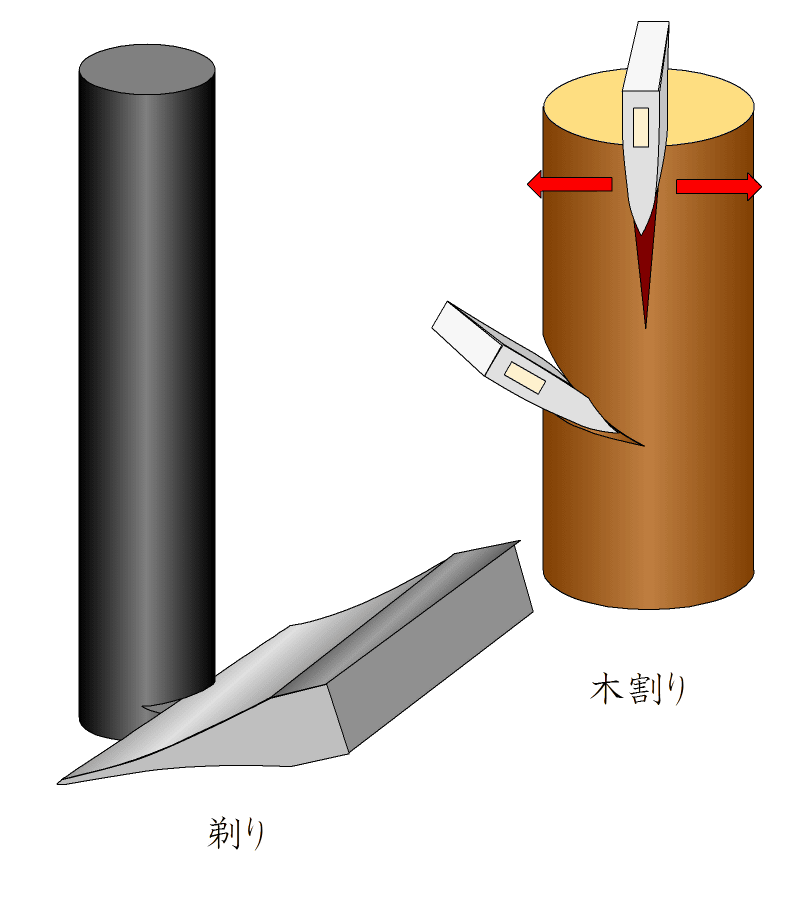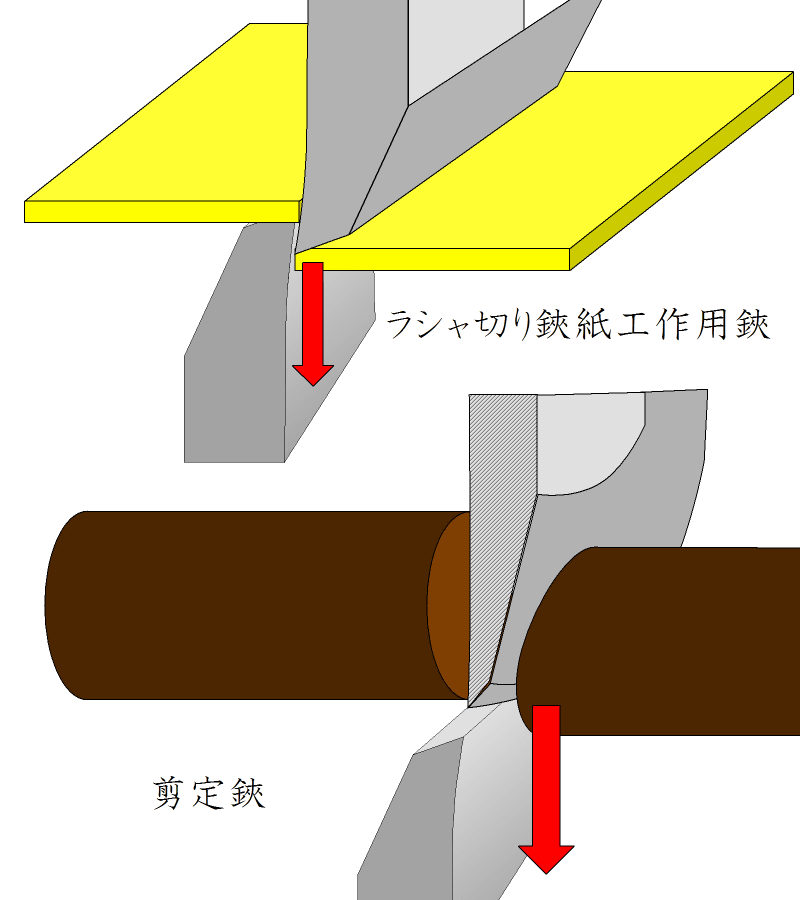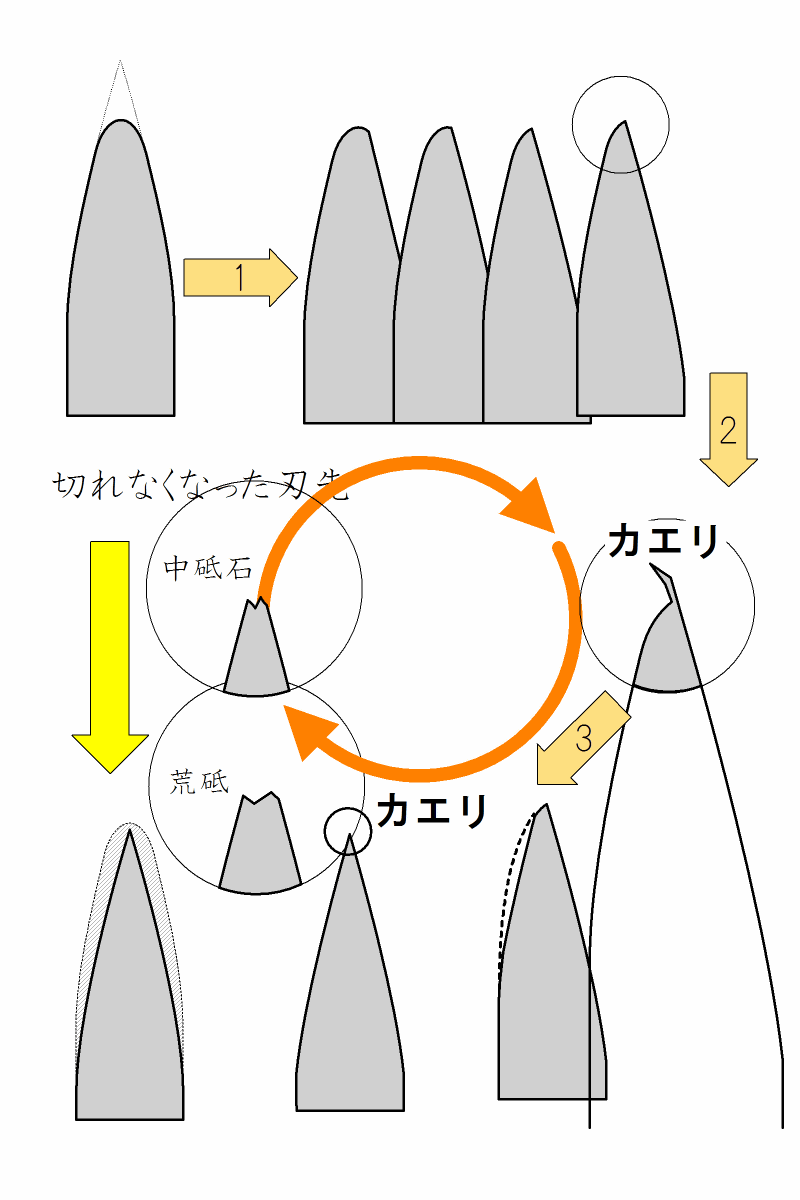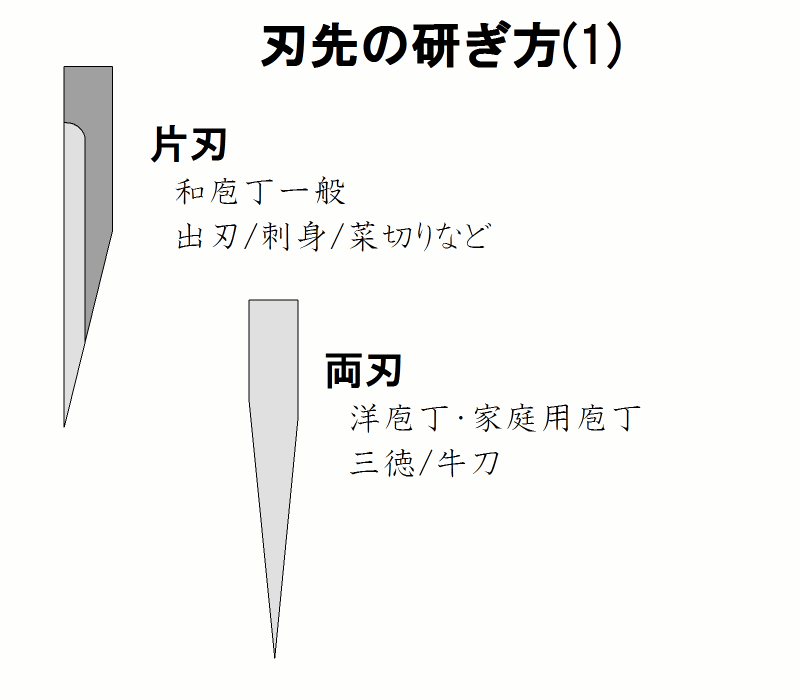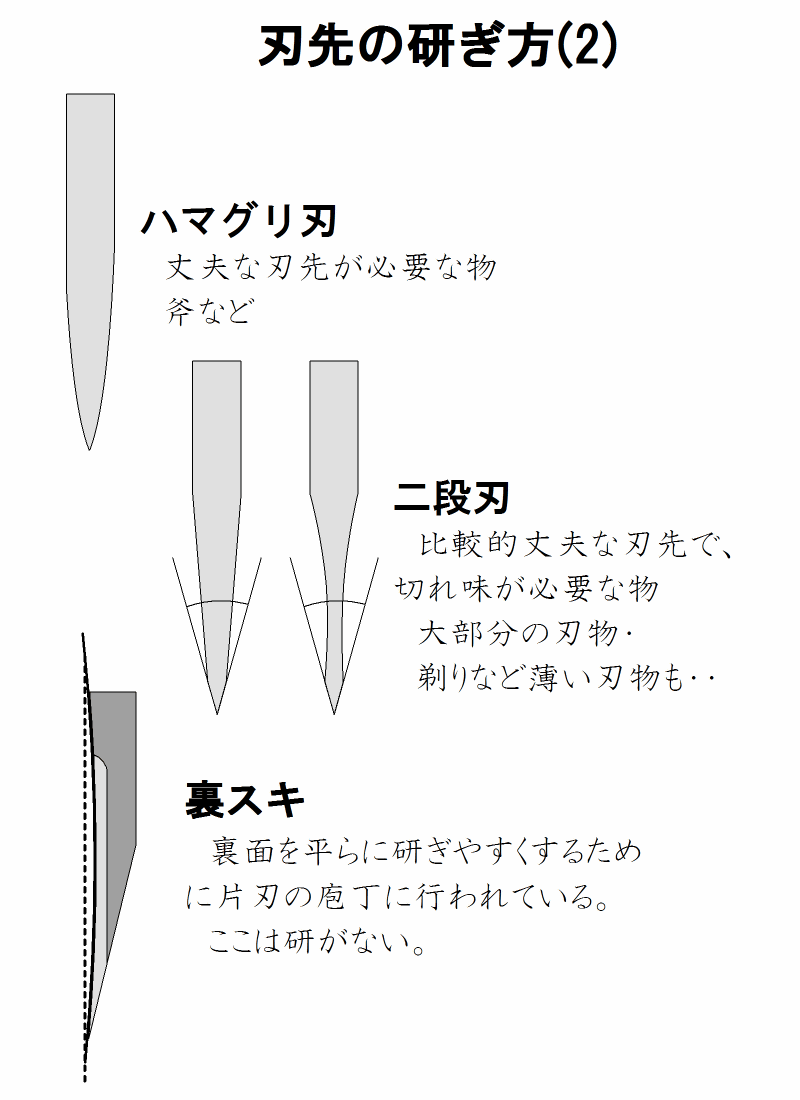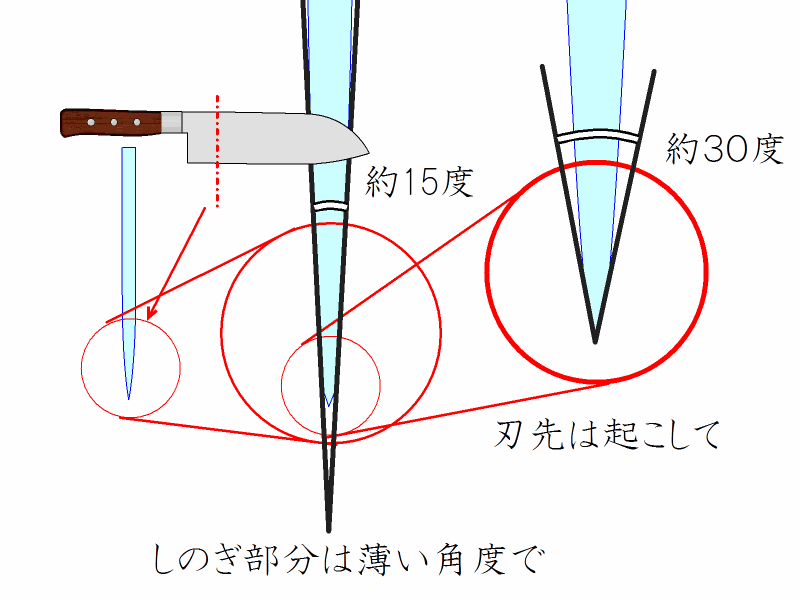ヒッタイトの滅亡後、製鉄技術は周辺にもたらされて以来、農機具や武器、そした様々な工作物と人類において鉄は最も重要な金属であり続け、産業革命以降は、益々その重要性は増しました。
鉄は、あまりに身近にたくさんあり、その重要性は極めて高い物資です。そして日本刀や和庖丁、そして高機能鋼材など日本は世界一の鉄を扱う技術を持ち、日本の重要な産業でもあるのですが、日本の学校教育では、まるで無視されていて、鉄や鋼の性質について触れられることはありません。
日本と鉄
鉄器は紀元前3世紀頃 青銅とほぼ同時期に日本へ伝来したが、当初は日本には製鉄技術はなくもっぱら輸入されていました。
製鉄はその後、弥生時代後期(1~3世紀)には、北九州や兵庫など各地で開始されはじめ、やがてたたらによる製鉄技術の登場により生産される鉄は日本の重大な産物となる。
(図1) 砂鉄
組成式 Fe3O4 で示される磁鉄鉱

P(リン)、S(イオウ)など有害元素を含まない極めて良質の鉄が得られるが、多くはチタンを含むため近代製鉄では製錬できない。
日本の製鉄法であるたたら吹きは鋼塊炉 (bloomery) を用いた、砂鉄を原料とする直接製鋼法です。一方で、踏鞴製鉄と呼ばれる間接製鋼法も行われていました。
たたら吹きは、砂鉄を木炭を用いて鉄の融点より低い温度で、低温で還元すして直接炭素鋼を得る方法で、銑鉄を経ないため、炭素の含有量が銑鉄より極めてひくい良質な刃物鋼を生成するもので、近代の製鉄法が確立する前は(漢代以降の中国などの例外を除いて)広く世界的に見られた方法です。
特筆すべきは、日本のたたらは、鉄の含有量が高く不純物をほとんど含まない良質の砂鉄を原料に用いてきたことです。この製鉄方法で、玉鋼や包丁鉄といった複数の鉄が同時に得られる特徴があり、後の日本刀を生み出す礎となりました。
戦国時代になると日本では、1550年代頃までに銃器の生産が普及し、当時は足りない鉄を輸入していたことも知られています。鉄の生産量が増え、鉄の利用が一般的になったこのころになると鉄の技術者は鍛冶師、鋳物師と呼ばれるようになり分業化も進みました。また、永代たたら
の普及により生産量が爆発的に増加したため、生産性の観点から歩止まりの良い砂鉄が採れる中国地方や九州地方への産地の集中が進むこととなった。
当時、鉄の精錬には木炭が使われた(ただし、宋代以降の中国においては石炭の利用が始まる)。日本の森林は再生能力に優れ、幸いにも森林資源に枯渇することが無かった。良質な砂鉄にも恵まれており、鉄の生産量と加工技術では世界で抜きん出た存在になりました。
ケラ押し法(直接製鉄法)
真砂砂鉄(チタン磁鉄鉱由来の砂鉄で不純物が少ない)を木炭と共に比較的低温で還元して玉鋼などの鋼を直接取りだす日本独自の製鉄方法です。収率が悪く製品にバラツキも多くなるが、極めて良質の鋼が得られる。
ズク押し法(間接製鋼法)
赤目砂鉄(フェロチタン鉄鉱由来の砂鉄)を木炭を用いて還元しますが、ケラ押し法に比較してより高温で行うために、炭素の多い銑鉄を取り出す。
取り出された銑は、大鍛冶という溶融しないで鍛錬によって炭素を取り除き、左下鉄、包丁鉄として利用されていきます。ズク押しで刃物鋼をつくる方法もかっては行われていましたが、現在日本刀の素材の玉鋼を取り出すのは、ケラ押し法によります。
真砂砂鉄は酸性岩類の花崗岩系を母岩とした砂鉄でチタン分が少ない。赤目砂鉄は塩基性岩類の閃緑岩(せんりょくがん)系を母岩としTiO₂に換算して5%以上のチタンを含んでいます。
江戸幕末には、艦砲を備えた艦隊の武力を背景に開国を迫る西洋に対抗するために、大砲鋳造用の反射炉が各地に建造された。これらは明治時代になるとより効率の良い高炉にとって代わられた。高炉はコークスを用いてより高温で炭素の多い銑鉄を連続的に生産できるようになった。